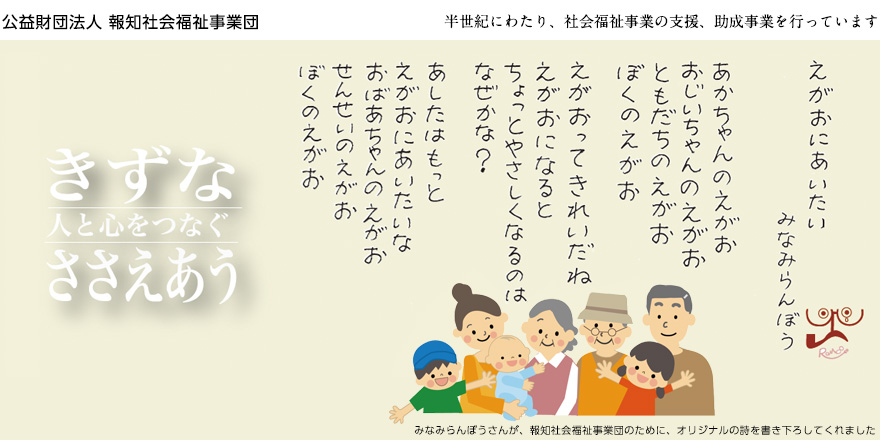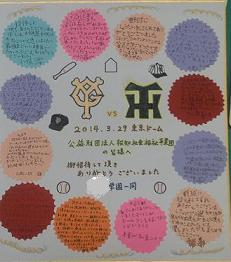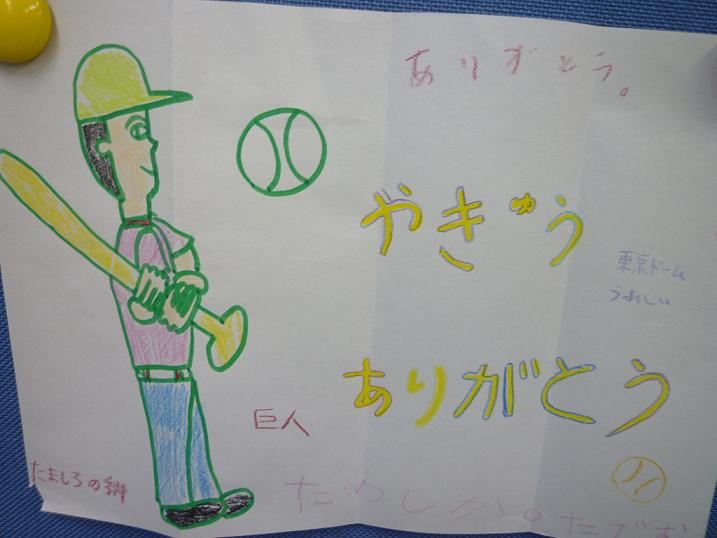当財団は、東日本大震災復興支援活動をしている10団体に助成を行っていますが、
そのうちのひとつ、一般社団法人ブッシュ・クローバ・コミュニティから、
「石巻市金華山復興支援植樹事業」の実施報告が届きました。
概要は以下の通りです。
太平洋に浮かぶ金華山は、震災の震源地に最も近く、津波と土砂崩れで大きな被害を
受けました。特に樹木が流されたため、毎年の大雨で、状況が悪化しています。
早急な植樹が必要と判断されるため、さくらの木を植樹することにしました。


実施期間は、4月10日から同25日まで。
金華山には、鹿が多く、苗木を食べてしまうため、1本ごとに防鹿柵を設置し、
柵内にさくら25本を植樹しました。
従来の防鹿柵の欠点を補い、構造を工夫し、しっかりした柵を作ることが出来ました。
苗木は120センチ程度の、大きめの山桜を選び、早く成長するように工夫しました。


****************************
ご苦労様でした。
今後、苗木の生長ぶりと、成木になって桜が咲いたときの報告が出来ればと考えます。
申請内容
金華山は、3・11で多大な被害が発生したにも関わらず、島全体が神社という特殊性から、行政の援助がほとんどなく、土砂崩れや津波で島内の桜や檜が倒木したままになっている。これを少しでも元に戻すため植樹活動を行う